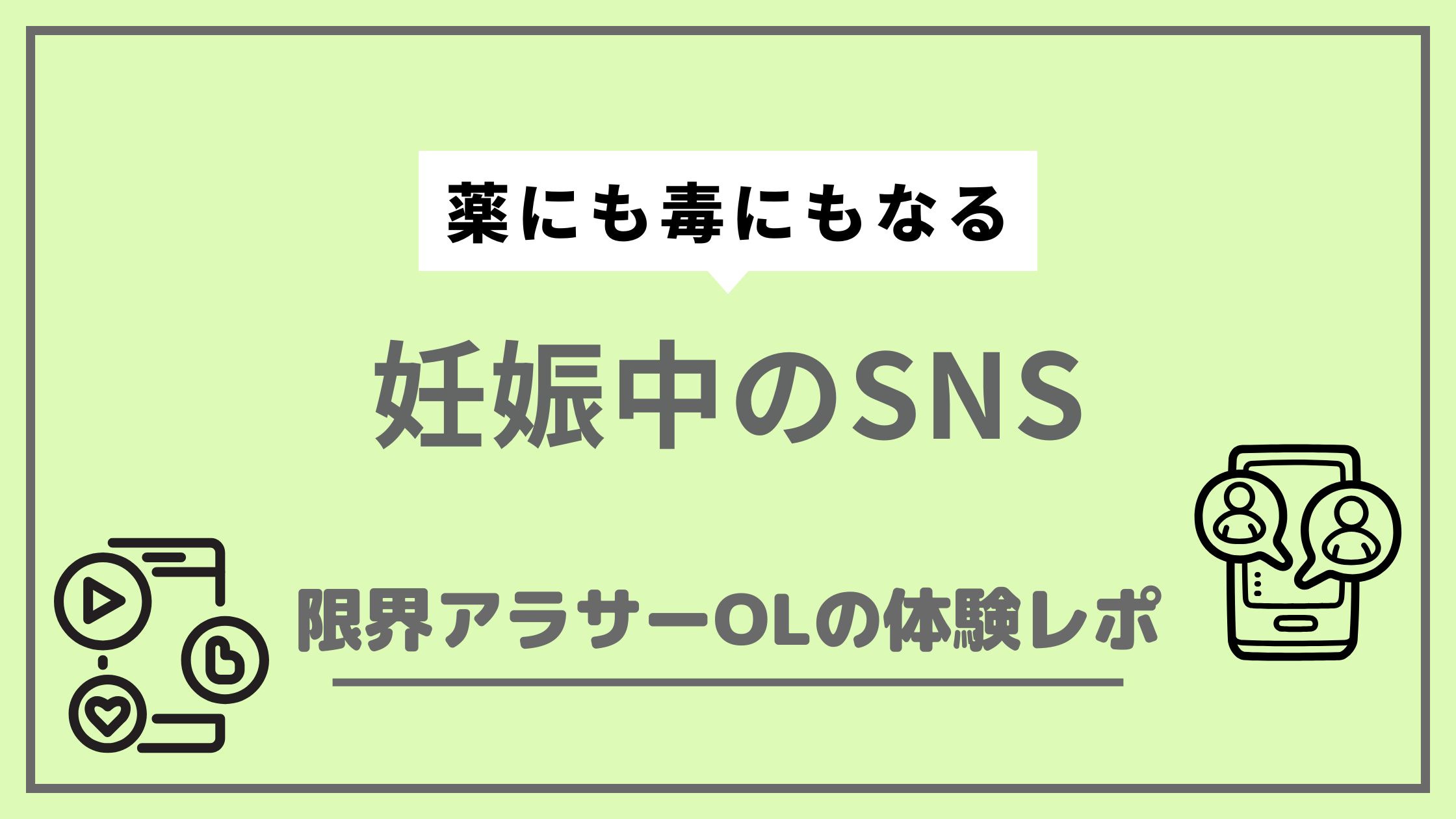今回は、妊娠中のSNSとの付き合い方についてお話しします。
私は妊活をしていた時からX(旧Twitter)を利用しており、妊娠後もXに加えてThreadsやInstagram、このホームページの開設などを通して、積極的に情報収集や発信を行ってきました。
もちろん、役立つ情報や励まされる言葉も多くありましたが、一方で自分にとっては必要のない、むしろ心の負担となる情報も少なくありませんでした。
現代のSNSは、こちらが望まなくても、アルゴリズムによって情報が勝手に流れてくる仕組みになっています。
特に妊娠中のように心が不安定になりやすい時期には、その「勝手に入ってくる要らない情報」に振り回されてしまうこともあります。
それがアルゴリズムの怖いところ。
私はそれに対して、自分なりの工夫で対処してきました。今回は、その具体的な体験と対処方法について共有させていただきます。
1. 助けられた「いい情報」
- 妊娠・出産・子育てに関するライフハックや便利グッズの紹介
- つわりで苦しい時期に、同じ週数の妊婦さんと励まし合えたこと
- 一人で家にいる孤独な時間に、「自分だけじゃない」と感じられたこと
- リアルで会えるプレママ友達と繋がることができたこと
SNSを通じて、共感や安心感を得られたことは、妊娠生活を乗り越える大きな力になりました。
これらに関しては本当にSNSをやっていてよかったなと思っています。
2. 心が沈んでしまう「悪い情報」
- 同じぐらいの週数の方の流産や死産に関する体験談
- 妊婦への攻撃的なコメントや心ない発言
特に、SNSのアルゴリズムによって一度でも関連する投稿を開いてしまうと、その後も似たような内容が繰り返し表示されてしまいます。
見たくないのに見てしまう――そんな悪循環に悩まされることが多々ありました。
3. 私なりの対処法
私自身、妊娠初期に流産を経験したこともあり、ネガティブな投稿を見るたびに「次は自分の番かもしれない」と不安な気持ちが人一倍強かったと思います。
実際、妊娠の壁まで不安になりながら指折りで数え、超えるたびに一安心、次の壁に向けてまた指折りで数える毎日でした。
データ的には稀なケースだと頭では理解していても、繰り返し目にすることでどんどん気持ちが沈んでいってしまいます。
ミュートや「興味がない」設定をしても、完全には避けられないのが現実でした。
そのたびに、冷静さを取り戻すためにデータを見直したり、ChatGPTに相談したりして気持ちを立て直す――そんな日々の繰り返しでした。
今振り返ると、そういう時こそSNSを一時的にやめるべきだったのかもしれません。
私はもともと「気にしすぎる」性格なので、SNSは向いていないと感じることもありました。
でも、「良い情報を逃したくない」「せっかくできたプレママ友達と繋がっていたい」という思いも強く、何とかSNSを続けながら、自衛に徹することにしました。
Xで実践していた主な自衛方法
- ミュートキーワードを細かく設定(50ワード近く登録してます(笑))
- ブロック機能の積極的な活用(100アカウント以上登録してます)
- フォローしている人の投稿だけを見る(おすすめ欄は見ない)
- それでも不快な投稿を目にしてしまった場合は、「興味がない」設定またはブロック
こうした対策を続けた結果、妊娠後期を迎えた今では、不安を煽るような情報はほとんど目に入らなくなり、心穏やかに過ごすことができています。
4. 最後に
SNSのアルゴリズムは、一度見た情報を「あなたに必要な情報」と判断し、似た内容を次々に表示させてきます。
そのため、「暗い話ばかりが世の中のすべて」という錯覚に陥ってしまいがちですが、実際にはごく限られた一部の情報が凝縮されて表示されているだけです。
それが世界のすべてではありません。
SNSは、情報を取捨選択できる人にとってはとても便利なツールですが、取捨選択が難しいと感じる方にとっては、心を乱す要因になりかねません。
妊娠中という特に繊細な時期だからこそ、自分の心と体を守るための「情報との付き合い方」を見つけてほしいと願っています。
それでは、全ての妊活戦士&ママに幸あれ!